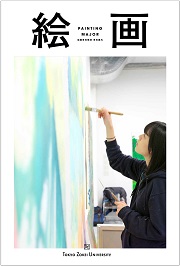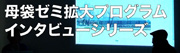11/22(金)避難訓練の様子
11/22(金)の夕方に避難訓練が実施されました。
各教室にいた学生が10号館絵画棟隣の芝生に集まりました。
近藤先生が全体へのアナウンスと東京造形大学作成の災害時対応マニュアルについての説明をしました。※災害時対応マニュアルは学生支援セクションに置いてあります。
無事に避難訓練が終わりました。寒い中でしたが、災害時の意識を高める良い機会になったと思います。
(助手:にしひら)
11/22(金)の夕方に避難訓練が実施されました。
各教室にいた学生が10号館絵画棟隣の芝生に集まりました。
近藤先生が全体へのアナウンスと東京造形大学作成の災害時対応マニュアルについての説明をしました。※災害時対応マニュアルは学生支援セクションに置いてあります。
無事に避難訓練が終わりました。寒い中でしたが、災害時の意識を高める良い機会になったと思います。
(助手:にしひら)
先日、形象表現2年生では専任・非常勤講師の5教員による座談会が行われました。
非常勤講師の先生方は毎週1日お越いただいているので全員が揃うことは年に数回しかない貴重な日です。
今回は先生方の中に2年生を交えて同じテーマを掲げて話し合いました。
終止笑顔の絶えないトークの場となりました。
ただ絵を描くだけでなく、この時代を生きるもの同士として考えや認識を学生同士、教員同士として共有することが大切なことであると感じました。
(助手: yasuyo maruyama)
2013年11月13日 カテゴリー:お知らせ, 個展・グループ展
ただいま大学内では「新具象彫刻展を出発とした東京造形大学の出身者たち」展を東京造形大学附属横山記念マンズー美術館、ZOKEIギャラリー、CSギャラリーの3会場で開催しております。
出展作家|麻田 昭作、浦野 八重子、奥田 秀樹、中ハシ 克シゲ、舟越 桂、三木 俊治、山崎 豊三(50音順)
今回東京造形大学附属美術館では、「新具象彫刻展」に出品した多くの彫刻家の中から、東京造形大学出身の7人の彫刻家の表現活動に着目しています。
本展は7人がこれまでに発表した作品を、「新具象彫刻展出品作」「新具象彫刻展以降の作品」「近作」の3つの時点に分け、それぞれを比較展示することで、7様の表現の変遷を辿ります。
写真は形象表現2年生の授業風景です。近藤先生による丁寧な解説を聞きながら展覧会を鑑賞しました。
対象7人の彫刻家たちが長年にわたり、彫刻と真摯に向き合うことで生み出された作品の数々は、学生にとっても良い刺激となったのではないでしょうか。
会 期|2013年11月4日(月)〜 12月7日(土)
休館日|日曜日・11月6日(水)・11月7日(木)・11月29日(金)・11月30日(土)
時 間|10:00〜16:30(入館は16:00まで)
観覧料|無料
会 場|東京造形大学附属美術館
(第1会場|横山記念マンズー美術館 第2会場|ZOKEIギャラリー 第3会場|CSギャラリー)
主 催|東京造形大学附属美術館
協 賛|東京造形大学校友会
協 力|ギャラリー砂翁&トモス
(助手: yasuyo maruyama)
アートプログラム青梅2013「雲をつかむ作品たち」と4大学学生展「蓋はなくなった」が11月2日(土)~12月8日(日)まで開催中です。
初日には青梅市立美術館にてオープニングレセプションとシンポジウムが行われました。東京都庭園美術館学芸員の関昭郎さんによる基調講演「アートはモノではない デザインはカタチではない」、また大橋紀生さんの司会で関昭郎さん、白井美穂さん、市川平さん、作間敏宏さん、原田丕さんによる座談会が催され活発な議論がなされていました。
東京造形大学関係の出品は、母袋俊也教授がサクラファクトリー、非常勤講師の白井美穂先生、卒業生門田光雅さんが青梅市立美術館、小島章義さんがBOX KI-O-KUに展示。
学生展は、院2わたなべももこ、院1内田菜生、岡崎シヲリ、小山友也、田神光季、椋本奈津子、学部4年生ユニット「\] 香月恵介、加藤フリーダ、合田聖美、花島拓也、松井千裕、山田彩香が出品します。
アートプログラム青梅2013:http://artprogramome.sakura.ne.jp/wp/?page_id=11
母袋俊也
白井美穂
門田光雅
小島章義
わたなべももこ(大学院2年)
内田菜生(大学院1年)
岡崎シヲリ(大学院1年)
小山友也(大学院1年)
田神光季(大学院1年)
椋本奈津子(大学院1年)
ユニット「\」 香月恵介(学部4年)
ユニット「\」加藤フリーダ(学部4年)
ユニット「\」合田聖美(学部4年)
ユニット「\」花島拓也(学部4年)
ユニット「\」松井千裕(学部4年)
ユニット「\」山田彩香(学部4年)
(助手 清原)
2013年11月8日 カテゴリー:お知らせ
現在、非常勤講師をされている元田久治さんと卒業生の大矢加奈子さんがhpgrp GALLERY TOKYOより「ART TAIPEI」に出展されますのでお知らせいたします。
元田久治、大矢加奈子、窪田美樹
「contiguous zone -領海-」
2013年11月2日(土) – 12月1日(日)
@AKI GALLERY (台北)
オープニングレセプション:11月9日 (土) 19:30-21:00
元田久治, 「Revelation-Kabukicho2」, 2013, lithograph, 610×490mm , Ed.10
大矢加奈子, 「星におねがい」, 2011, oil, gesso, cashew on panel, 1303×970mm
<開催概要>
・会期:2013年11月2日(土) – 12月1日(日)
・会場:AKI GALLERY
10369 台北市民族西路141號
http://www.galleryaki.com/aboutus.php?lang=en
・入場料:無料
・参加ギャラリー / アーティスト:
ギャラリー小暮 / 平林貴宏、山本タカト、瀧下和之
hpgrp GALLERY TOKYO / 元田久治、大矢加奈子、窪田美樹
YOD Gallery / 佐竹龍蔵、向井正一、杉山卓朗
・ウェブサイト:http://www.galleryaki.com/exhibition-current.php?lang=en
(助手 清原)
2013年11月1日 カテゴリー:授業の様子
先日のガイダンスに引き続き、各自の選択した指標のワークショップがはじまりました。4つの研究指標ごとに、3日間のワークショップを2回繰り返して開きます。その中から2つのワークショップを選択受講し、どの研究指標に進むべきか考えます。
概念表現研究指標「マイ・フェイバリッツ」自分の実作品をもとにして、面談をしながら、ドローイング、プランニングを行う。
形象表現研究指標「身体から意識への環流」F30号大のドローイングを制作。3日で3点提出。
広域表現研究指標「すべてのことをこの1曲から」あなたが好きなCD1曲をもってきてください。
版表現研究指標 1:カッターメゾチント 2:版表現について・転写からのドローイング 3:ガリ版印刷を使った制作。
今後の展開が楽しみです。
(助手:にしひら)
2013年10月31日 カテゴリー:お知らせ, 個展・グループ展
展覧会 アートプログラム青梅のご案内
11月2日より「アートプログラム青梅<雲をつかむ作品たち>」が開催されます。今年度の本学関係の出品者は、母袋俊也教授、非常勤講師・白井美穂先生、卒業生・門田光雅、小島章義。在校生は大学院2年生・わたなべももこ、大学院1年生・内田菜生、岡崎シヲリ、小山友也、田神光季、椋本奈津子、学部生ユニット「\」(スラッシュ)・香月恵介、加藤フリーダ、合田聖美、花島拓也、松井千裕、山田彩香になります。
ご高覧頂けますようよろしくお願い致します。
アートプログラム青梅2013. 出品者一同
(助手:青木)
2013年10月30日 カテゴリー:授業の様子
1年生研究指標選択ガイダンスが行われました。形象表現、概念表現、版表現、広域表現の4コースから二年次以降のコースを決める重要な説明会です。
先生方が各指標について詳しく説明をされていました。形象表現研究指標ご担当の右:近藤昌美先生と左:小林良一先生。
明日より各研究指標のワークショップがはじまります。
ワークショップの様子はまた後日掲載します。
(助手:にしひら)
2013年10月25日 カテゴリー:個展・グループ展
1983年卒業のOBの野村俊幸さんの個展が銀座のステップスギャラリーであリましたので行って来ました。
http://www.youtube.com/watch?v=kn9aeVBjLzs
(教員:近藤 昌美)
カテゴリー:個展・グループ展
客員教授の中村宏先生の個展が銀座のギャラリー58において開催されました。中村先生は1932年生まれで、長く本学の非常勤教員、客員教授をしていただいて来ており、非常にタフな作家活動は学生のみならず、我々教員にも素晴らしい刺激になります。
(教員:近藤 昌美)