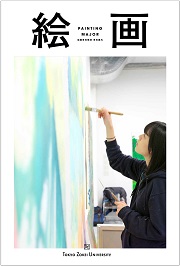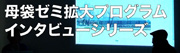堀先生送別会1/11,2012
2012年1月15日 カテゴリー:その他
形象表現の非常勤教員の堀由起子先生が任期にともない離れることになり、学生達主催の送別会が学内で開かれました。2年から4年までお世話のなった学生達が大勢集まってくれました。
中央が堀先生です。学生達からの手作りの記念寄せ書き作品を受け取り拍手に包まれました。堀先生。お疲れさまでした。大学は離れますが、学生達との作家としての交流はずっと続きます。
(教員:近藤 昌美)
2012年1月15日 カテゴリー:その他
形象表現の非常勤教員の堀由起子先生が任期にともない離れることになり、学生達主催の送別会が学内で開かれました。2年から4年までお世話のなった学生達が大勢集まってくれました。
中央が堀先生です。学生達からの手作りの記念寄せ書き作品を受け取り拍手に包まれました。堀先生。お疲れさまでした。大学は離れますが、学生達との作家としての交流はずっと続きます。
(教員:近藤 昌美)
新年が明けて授業が始まると学部1年から院1までの講評が各指標連続して開かれます。我々専任教員にとってはそのすべてに参加するので体力勝負な一面もありますが、1年間の教育の成果を観測出来る機会でもあります。
形象3年の講評風景です。130号程度+派生小作品という課題でしたがそれを上回る制作量の学生が多く、充実してました。
これらは形象2年です。2年生は制作に欲が出て来た者とまだそれほどではない者の差が少し出来てましたが、3年になるとそれも少なくなって行くと思います。
上は院1年の中間発表ですが、主査、副査教員からそれぞれ講評を受けます。院は美術館やギャラリーに展示ですので、プレゼンテーションの力も問われます。
これらは学部1年の最終課題の講評です。2年からは4指標に分かれますので全体での講評はしばらく無くなるわけですね。1年生は全体を3つのグループに分け、この初日は28名の作品を3名の教員が3時間かけて講評しましたが、それでも上の学年の指標での講評に比べ一人当たりの時間が短く今後も工夫して行かなくてはと考えています。
(教員:近藤 昌美)
2012年1月10日 カテゴリー:個展・グループ展
明けましておめでとうございます。本年も東京造形大学絵画専攻をよろしくお願いします。
さて、新年最初の学生展に行って来ました。院2年の藤原佳恵さん(主査教員:近藤)が千代田区の3331Arts Chiyoda内のゼロダテアートセンターで個展が始まっています。http://www.zero-date.org/schedule/
公開制作という形で、Ⅰ/7〜9までの3日間会場で制作していました。彼女は院の修了制作の提出期限前のリスキーな個展開催でしたが、忙しいくらいがアーティストとしてはちょうど良いのかも知れませんね。
(教員:近藤 昌美)
2011年12月20日 カテゴリー:個展・グループ展
銀座や京橋のいくつかの画廊では年末の小品展が開かれているようです。参加している卒業生からDMをもらったので行って来ました。本来なら、他のギャラリーにも回るはずでしたが時間的に間に合わずこの銀座のギャラリーQまでしか回れませんでした。http://www.galleryq.info/exhibition_now/exhibition_now.html
今回のギャラリーQの小品展は31名の作家が参加していましたが、その内の3名が本学絵画出身でした。
これらは07年院修了の内藤瑞樹さん(主査教員:高橋)の作品です。
上の作品は2000年学部卒業の村尾成律さんの作品と、下は左から内藤さん、村尾さんです。
こちらは2010年学部卒業の小林希さんの作品ですが、残念ながら本人には会えませんでした。
頑張っている作家がいて、それを支えるギャラリーがあるということは素晴らしいですね。
(教員:近藤 昌美)
カテゴリー:個展・グループ展
概念表現2年生の平田梨花子さんが豊島区のターナーギャラリーで個展を開催中ですので行って来ました。23日まで。http://www.turner.co.jp/gallery/event/111217-02.html
平田さんは昨年このギャラリーで行われたデッサンコンペのグランプリを獲得し、その副賞として今回の企画展となったようですが、いろんなコンペがあるものだと思いました。
「母子は語る」と題された今展は、初個展なのでしょうか、やや会場の広さを持て余している印象でしたが、2年生らしく荒削りながら元気の良さが好印象でした。
巨大なトン足のオブジェクトを中心にしたインスタレーションです。
(教員:近藤 昌美)
2011年12月19日 カテゴリー:個展・グループ展
美大生の総合展覧会と銘打ち毎年学生主体の企画で行われている展覧会「THE SIX」を会場であるラフォーレ原宿で見て来ました(12/16〜18)。本学からも運営に参加している学生もいるようですが、コンペ形式の展示に形象表現3年の大久保薫君が入選し展示していましたので。
全体の印象は、お祭りという感じで、若い感覚は面白いと思いましたが、アートか粗びき団かの区別がつかないものまで混淆してましたね。http://www.lapnet.jp/event/event_l111216/
大久保君の作品です。こうした、小さなチャンスにもどん欲に関わっていく姿勢は良いと思います。
(教員:近藤 昌美)
カテゴリー:レクチャー・ワークショップ
形象表現の金曜日を担当している薄久保先生の授業に、活躍する卒業生として大野智史さんをお迎えしてのレクチャーがありました。大野さんは薄久保先生の同級生でもあり現在は小山登美夫ギャラリーの作家として国内外を問わず活躍しています。今回もデンマークでの個展を控え忙しい中来てもらいました。
http://www.tomiokoyamagallery.com/artists/ohno/
絵画アトリエ多目的室において形象表現2年対象のレクチャーでしたが、他学年や他指標の学生がたくさん参加していました。手前は企画した薄久保先生です。
前半はプロジェクターで自作紹介の形式でしたが、後半は希望者のアトリエを回り作品批評をしてもらいました。作品だけで生活している身近な先輩の話が聞けるということは、かえがたい刺激になったと思います。
(教員:近藤 昌美)
2011年12月14日 カテゴリー:個展・グループ展
私が企画した学内CSギャラリーでの展覧会「Remedy」が始まりました。学部生の二人がどのくらいクオリティーを上げられるかが心配でしたが、全体的に面白い展示になったと思います。学外からも数名来られた方もあり同級生を中心ににぎやかなオープニングパーティーになりました。こうした出品者にとって晴れやかなイベントも作家意識を醸成してゆく上で大切なことだと思っています。作家は他者と交流する力も大事です。展覧会は20日までですので、ぜひご高覧下さい。
ギャラリーは絵画アトリエのあるCSプラザの1階にありますので学生達がたくさん来てくれました。
左右の二人ずつが出品者の学生と助手です。左から西原君、秦君、私、村上さん、青木さんです。各人には来場者の前で自作の対する思いも語ってもらいました。
各作品は近日中にアップします。
(教員:近藤 昌美)
カテゴリー:個展・グループ展
銀座のギャラリーゴトウで卒業生の武内明子さん(08年学部卒業、版表現)が個展を開催中ですので行って来ました(12/9〜17)。http://www.gallery-goto.com/
彼女は個人としても精力的な活動をしていますが、やはり卒業生である麻生知子さんと「渡り鳥計画」というユニットでも作家活動をしていて、次回の若手絵画作家の登竜門であるVOCA展にもユニットで推挙されて出品するそうです。
(教員:近藤 昌美)
2011年12月6日 カテゴリー:個展・グループ展
来週火曜13日から20日まで学内CSギャラリーにおいて、Remedyと題した助手と学部3年生2名ずつ4名によるグループ展が始まりますのでお知らせします。
これは、私が学内でコンセプチュアルな作品を指向している者達を取り上げて企画したものです。日頃はペインティング作品を中心に活動している学生を指導しているのですが、今回はその対岸にあるかのような作品指向を選び、展覧会として問いかけてみました。学内向けではありますが、学部1、2年生に近、現代美術史にもっと興味を持って貰いたいと思い、教育的な側面からの企画です。
参加者は、rgb+ 2011展にも参加している助手の村上真之介さん、青木豊さんと学部3年の形象表現指標の西原史尋さん、概念表現指標の秦義也さんです。
以下は、DMフライヤーに載せた私が書いたステートメントです。
『コンセプチュアルアートというカテゴリーが喧伝されて既に数十年が経つ。視覚芸術の文脈として言を左右することもない位置が成り立って久しい。しかし、昨今の情緒的な作風が目立つ日本の美術状況の中では、その概念性を表象の骨子に置いた作品は少数派だと言えるかも知れない。だが、本学の卒業生作家、在学生を見回すと、情緒を剥ぎ取るかのような概念性の強い作品を作り続けている者たちがいるのも事実だ。
そこで、今企画はついえぬコンセプチュアルアートの系譜を学内に探してみた。
Remedy(レメディー)とは、自然治癒力を高めて病気を治すホメオパシー治療で使われる砂糖玉のことである。果たして、アートにおける様式としての“概念性”は、他方で偽科学であると揶揄されるホメオパシーのレメディーの様に有効性の幻想であるのか、または実効性のあるアートの文脈であるのかを、この学内の末裔達に問いたい。』
rgb+展とは1週間重なっていますので、二つともご高覧いただければ幸いです。
(教員:近藤 昌美)